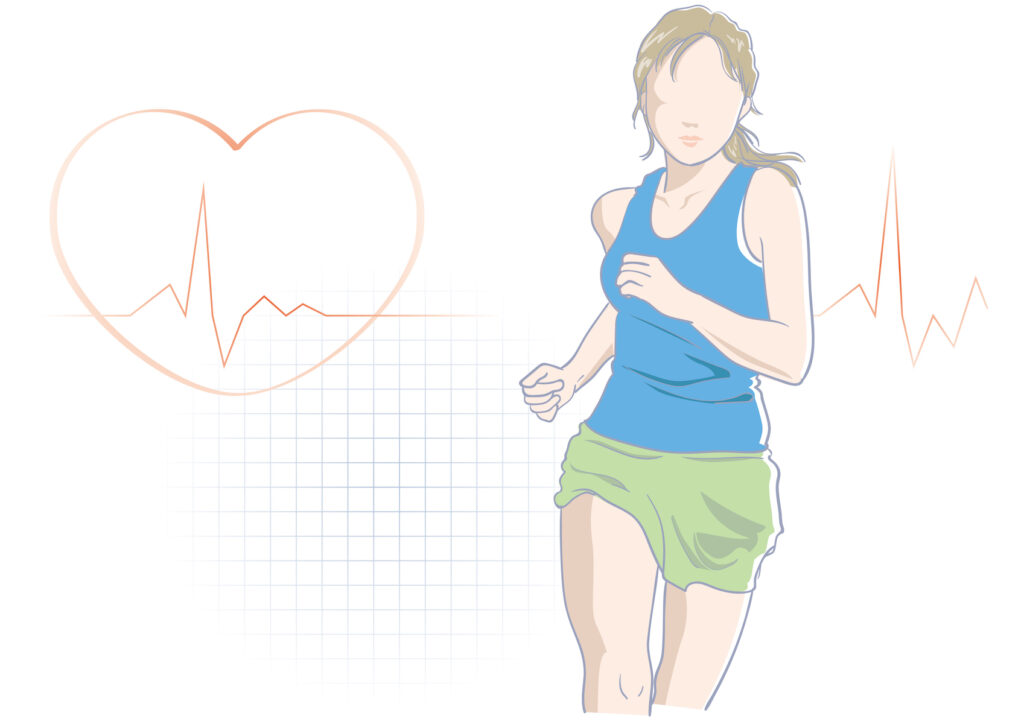スポーツ心臓
スポーツ心臓とは、心臓の加齢しやすい体質を持っている方が、運動による強い負荷をかけ続けることで、心筋の肥厚、心臓の拡大、不整脈などの心臓の加齢を起こす現象です。
心臓の加齢しやすい体質とは、冠動脈と全身の動脈が収縮しやすい体質と、自律神経の興奮により頻拍を起こしやすい体質です。冠動脈が収縮しやすい素質は程度にもよりますが5人から10人に1人が持っていると考えられ、全身の動脈が収縮しやすい体質も同時に併存しやすく、運動時の高血圧を持っている頻度が高いです。また自律神経の興奮により、運動時頻拍の起こりやすい体質も心筋の障害の原因になります。若い頃から障害をきたすこともありますが、若い頃は心臓の能力に余裕がありますので、加齢とともに少しずつ問題が起きてくる方が多いようです。
サッカー、陸上、テニスなどスポーツをしているうちに、息切れ、胸の締め付け、胸痛、脳貧血、失神、動悸をきたす方のベースには、冠動脈の収縮である冠攣縮による酸素供給の低下、運動時の高血圧による酸素消費の増大、また自律神経興奮による頻拍に伴う酸素消費の増大があり、心筋虚血が結果として心筋障害を起こします。心筋障害は電気的障害であるブロック、頻拍、期外収縮、心房細動や心室頻拍を起こし、また形態の変化である心筋肥厚、心臓拡大、心筋変性をきたします。
スポーツ心臓の診断では、症状や家族歴の聴取、心音の異常、胸部のレントゲンで心臓の拡大、次に心電図でリズムの異常と心筋変性の電気的シグナルを確認します。精密検査としてはまず心エコーで心臓の部屋である心房心室の拡大、心筋の厚み、心筋収縮、心筋の硬さを調べます。次にホルタ-心電図を用いて不整脈、冠動脈の攣縮を調べます。さらに運動負荷心電図を用いて、運動時の頻拍、運動で誘発される高血圧、冠動脈の攣縮、器質的冠動脈病変などを調べます。
スポーツで症状が出る場合は、まずは日常生活で喫煙、飲酒、カフェイン、ブルーライト、睡眠不足、野菜やミネラルの不足などの問題を確認します。次に冠動脈の血管内皮障害や冠攣縮に対してEPA、Ca拮抗薬、冠拡張薬の投与を検討し、脈拍の異常に対してβ遮断薬やCa拮抗薬の投与を検討していきます。心房細動に対しては投薬とアブレーション治療を検討します。スポーツの現役中は競技中に事故をおこさず、障害が将来に残らないサポートと投薬を考え、スポーツ現役を引退すれば適度な運動負荷と必要に応じた投薬によって将来の予後を改善することを考えていきます。
まとめ スポーツ心臓は、運動時の冠動脈収縮、高血圧、頻拍などの体質を持つ方が、強い運動負荷を長時間かけることでおきてくる心臓の電気的および形態的な老化現象です。運動時に、息切れ、胸の締め付け、胸痛、動悸、失神をきたす現役あるいは元アスリートの方は受診をお勧めします。(爽心会 心臓クリニック藤沢六会 磯田 晋)