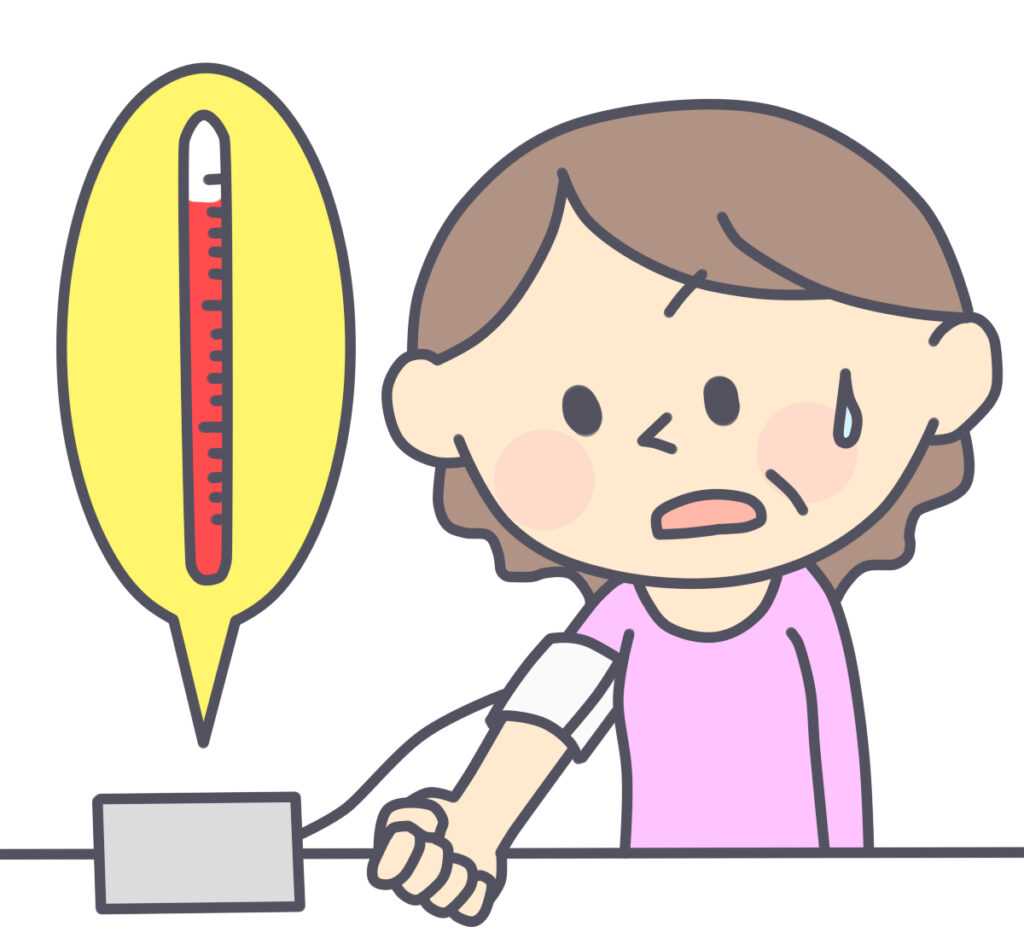血圧の変動が大きい
上の血圧(収縮期圧)が高い時は180あるのに低い時は100、この変動はなぜ?と思われる方は大勢いらっしゃいます。比較的ご高齢の方、緊張症の方、早朝高血圧の方、あるいは狭心症になりやすい血管攣縮性の高い体質を持っている方に起きる現象です。一般的な血圧の目標は上が130以下,下(拡張気圧)が80以下ですが、一体血圧が高い時と低い時のどちらを目標にすればよいのでしょうか?と悩む方は多いです。とりあえず、平均値で考えて、平均が血圧目標以内ならよろしいとしてください。
さてなぜこのような血圧の変動が生まれるのでしょうか。若いころは血管はゴムの管のように柔らかく、血液の量が変動すると血管がしなやかに広がることで、血液量の変動を吸収しますので血圧は変わりません。残念ながら加齢によってゴムの管が硬くなってきますので血液の量が少し増えただけで血圧が上がってしまいます。逆に汗をかいたりして血液の量が減ると血圧が下がりすぎます。加齢以外の血圧変動の大きい原因としては、血管攣縮を起こしやすく狭心症になりやすい体質を持っている場合があります。息切れ、締め付け、胸痛、動悸、不整脈、脳貧血を起こしやすい方はご相談くださいね。
朝血圧が高く、昼、夕方になると血圧が下がる方は早朝高血圧と呼ばれます。寝てる間に手足の血管が締まって、朝起きるとアドレナリンが出て血流が増えようとしますが、血管が締まっているので血圧が上がってしまいます。活動していると徐々に血管が開いて血圧が安定します。
病院に来ると緊張してアドレナリンが分泌されて、神経が興奮するために、血圧が上がることを白衣高血圧と呼びます。その逆で朝血圧が高いのに、来院するころには血管が開いて血圧が低めになる方は仮面高血圧などと呼ばれます。いずれにせよクリニックに来た時の血圧だけを目標にすると、時にコントロールが不適切になることがあります。クリニックだけでなく自宅でも血圧を測定して、朝と夕方など、時間を変えて血圧を測定することをお勧めします。
上の血圧が高いと心臓に負担がかかります。下の血圧が高いと全身臓器の血管に負担がかかり、脳や腎臓に障害が起こりやすくなります。この全身臓器の障害を防ぐために主に降圧剤を用いて高血圧を治療します。一方血圧低下は眩暈、立ち眩み、意識消失をきたしやすくなります。血圧の変動が大きくなった方は、厳格な血圧管理が難しくなります。平均的な上の血圧は130以下に、平均的な下の血圧が80以下になるように降圧剤を調節していきますが、この目安で降圧剤を調節していくと血圧が低めの時に上が90台や80台になってしまうこともあります。上の血圧がこのように低い時に、めまいや立ち眩みが起きてしまうのは脳血流が維持できていませんので、目標血圧を少し高めにして、降圧剤は少し減らす必要がありそうです。血圧の上が低めになるときに100程度は確保するのが安全です。結果として上が高くなる時は180あるいは200を超えるのを許容する必要がある方もいらっしゃいます。
血管の硬さが血圧変動の大きさの原因の一つですので、血圧の変動が大きめの方は、運動、魚食、大豆食、EPAの摂取、適切な降圧剤の選択などを通じて血管の硬さを改善していく必要があります。また脈波計測で血管の硬さをモニターしていく必要があります。
血圧変動の大きい方は、運動時に血圧が変動することがよくあります。安静時には正常血圧の方が、運動の負荷で上の血圧が200以上になることはよくあることです。心臓は上の血圧に対して仕事をしますので、運動時に上の血圧が上がる方は、心臓の負担が増えます。上の血圧が120の方が運動時に240にあがる方は心臓の負担が運動時に2倍に増えますので、息切れなどの症状が起こりやすくなります。運動時の血圧を運動負荷検査などで調べると、運動時の息切れや胸痛の原因を調べ、スポーツ心臓の予防のための対処をすることができます。また血圧が上がる状況として、風邪などの感染による体調不良、脳梗塞のような脳血流障害が原因であることがあります。血圧が大きく上がったら相談してください。
まとめ:血圧の変動が起きい方は加齢による血管の硬さが進んでいたり、血管の収縮や狭心症を起こしやすい体質を持っていることがあります。在宅の血圧計測、脈波計測や運動負荷試験で調べて、運動習慣、EPAや適切な投薬で血管を柔らかくしていきましょう。(爽心会 心臓クリニック藤沢六会 磯田 晋)